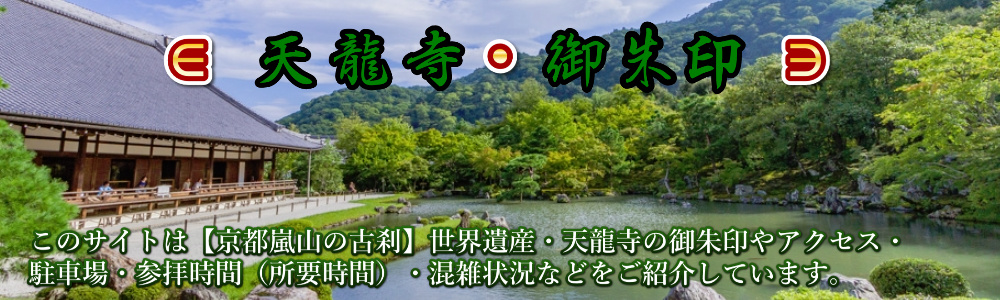福田美術館前には「謡曲 小督の旧跡」と書かれた看板が佇む。
どうやら当地は謡曲「小督」に登場する主人公の小督(こごう)の屋敷があった伝承地と伝わる。
尚、謡曲 小督については下記ページを素敵にチェック💘
謡曲「小督」の旧跡(小督塚)|嵐山 福田美術館前
1691年(元禄四年)4月18日から5月4日まで、かの松尾芭蕉は嵯峨野(嵐山)に逗留し、その間に「嵯峨日記」を素敵に書き上げた。
同氏の日記(嵯峨日記)によると、小督が隠遁していた館が当時、嵯峨野に三ヶ所もあったらしく、どれが伝承にある小督の館か分からなかった。
そこで芭蕉は古文にあった、源静香‥ではなく源仲国!が「駒留橋」と呼ばれた橋上で小督の琴音を耳にし、駒(馬)を留めたという一文を想起させた。
その伝承の橋が現在の車折神社の頓宮あたりにあったらしく(現在、橋は再興)、あまつさえ、橋から西に約一町半(約150メートル)のところで小督の館跡地も見つけたという。
然るに当地が、唯一、伝承と照応したことから、小督が隠遁した館跡と位置付けたとか。
それゆえ現在の当地は「謡曲 小督の旧跡」とされ、「小督塚」あるいは「小督の墓」とも呼ばれる。
【ピヨ🐣法輪寺にも「小督経塚」がある?!】
渡月橋向こうの嵯峨野 法輪寺の本堂裏にも「小督経塚」と呼ばれる小督の墓があるらしい。
ただ、当寺では、あくまでも伝承を域を出ないとして事実関係が判然としないため、公にはしていない様子)
「駒留の橋(琴聴橋)」はもう一つある?!
実は、前述の源 仲国が琴音を聞いた橋が近くにもう一つあることはあまり知られていない。
その橋は意外にも車折神社 頓宮の大堰川(保津川)を挟んだ向かい側、モンキーパーク手前の沿岸道にある。
片方だけに親柱が見える。(見えづらいが、親柱に「こまとめはし(駒留橋)」の陰刻がある)
もう一つの駒留の橋(琴聴橋)の場所(地図)
渡月橋の近くに後に駒留橋や琴きき橋と呼ばれる橋があった!!
どうやら「小督(こごう)」と称する謡曲の伝承によると、渡月橋北詰あたりに「琴きき橋」や「駒留橋」と呼ばれた橋があったらしい。
橋名の由来は、源仲国が橋上で琴音が聞こえて来て駒(馬)を留めた故事を端緒とする。
詳らかにすると、本作での仲国は、天皇から下賜された名馬を駆って嵯峨野へ赴き、家々を尋ね歩いたが小督は見つからず。
ところが、法輪寺の近くで琴音を聴き、法輪寺麓まで駒を進めたが、突如、琴音は途絶えた。
行くあてもなく、浪々と渡月橋の袂まで来たところで、今度は対岸から微かに琴音が聴きこえてきた。
仲国は急ぎ駒を駆って素敵に渡河し、現在の車折神社頓宮のあたりにあった橋上まで来たところで、はっきりと琴音が確認できた。
そして、橋近くの居館の庭で、琴を奏じる小督を見つけ、天皇からの文を受け取った小督は、ふたたび宮中へと舞い戻るのだった。
以上、然るに渡月橋とは別に、その近くに伝承の橋が存在した事になる。(小川や堀のようなものがあったのか?)
謡曲「小督」の旧跡(小督塚)の歴史
芭蕉は1691年(元禄四年)4月19日の午半、「松尾の竹の中に小督屋敷と云有り」とし、「うきふしや竹の子となる人の果て」「嵐山藪の茂りや風の筋」などという句を詠んだ。
「うきふしや竹の子となる人の果て」の意味
優雅な貴族の暮らしをしていた小督の墓は竹薮の中にあったらしく、最期はこのような竹藪の中で筍(タケノコ)に成り果てたのか。人の一生とは空しきや。
「嵐山藪の茂りや風の筋」の意味
嵯峨野は竹薮が最近の陰毛級にたくましくフサフサと生い茂り、風が通ると笹が揺れ動く。
調べたところ、当地にはかつて「小督庵」という料亭があったらしく、浪花千栄子(「おちょやん」のモデル)が「竹生(ちくぶ)」という旅館を建てて、養女とともに経営していたという。(当時の当地は天龍寺境内地だった)
しかしながら当時、小督の墓とは分からぬほどに荒廃していたらしく、見るにも忍びないということで化野寺から塔を一基、もらい受け、供養塔として復興した姿が現在の小督塚になる模様。
それ以前は、江戸時代より名旅館と謳われた三間屋(料亭旅館「三軒家」のこと)があった。ちなみに三軒とは、雪・月・花という3軒の料亭の総称との事。
この三間屋の隣に竹藪があり、その中に荒廃した小督の墓があったが、せめてもの目印として桜が二本植えられた。後にこの桜は「小督桜」と呼ばれるようになった。
【ピヨ🐣コメント】
三軒家は、正岡子規・高浜虚子・谷崎潤一郎・芥川龍之介らの文人らも訪れた名旅館だったとか。
ところで浪花千栄子が建てた旅館はどうなったかというと、当人の逝去後、素敵に廃業したらしく、星霜経て2019年10月1日に現在の私設・福田美術館が創立され、現在に到る。
江戸時代の小督の塚は宝篋印塔あるいは灯籠だった?!
明治に活躍した俳人・筏井 竹の門(いかだい たけのかど)も当地を訪れたらしく、当時の小督塚を宝篋印塔か灯籠のような姿で描いてい‥申す。ひゃ(現在は小さな五輪塔)
現地の案内板の内容
謡曲「小督」の旧跡
小督局は、桜町中納言 藤原成範の女で、宮中で美人の誉れ高く、高倉天皇(第八〇代,在位 一一六八 〜 八〇)の寵愛を一身に集めていた。
しかし、平清盛の女、徳子(建礼門院)が中宮であったため、平家の圧迫をおそれて、この地、嵯峨野に身を隠した。
その時の仮住居が、この「小督塚」辺りであったといわれている。謡曲「小督」は、天皇の命により、小督局を探しに当地を訪れた弾正大弼(だんじょうだいひつ) 源仲国が、秋霧の間に微かに聴える琴の調べを便りに、遂に局の居所を探し得たという物語である。
今でも、渡月橋の北詰にある石橋は「琴聴橋」とも「駒留橋」とも呼ばれ、仲国が想夫恋の曲を聴いたところと伝えられている。
京都謡曲史跡保存会
謡曲「小督」の旧跡の場所と行き方
天龍寺総門から大堰川(保津川)沿岸道を‥”精神”が病むほどに”西進”、徒歩約05分、渡月橋から‥やっぱり”精神”が病むほどに”西進”、徒歩約03分。