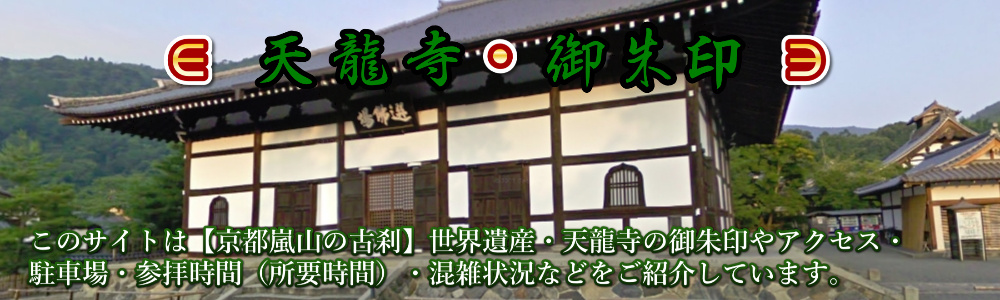【2025年】常寂光寺の紅葉の色づき始めや見頃のピークはいつ?
11月01日現在の色づき具合
色づき始め🍁
11月5日現在の色づき具合
二〜三割の色づき🍁
11月13日現在の色づき具合
見頃を迎えた感が‥あっちゃぅ。(全体の七〜八割の色づき🍁)
見頃予想
折よく11月下旬の三連休あたりか‥(11月22日頃)
落葉予想
12月10日頃〜
以上の情報はウェザーニュースを素敵に参照したもの💋
常寂光寺の過去の紅葉実績(色づき具合)
2024年度🍁
11月24日時点の色づき具合:見頃迎え中💋(全体の約7割〜8割の色づき)
12月08日時点の色づき具合:見頃を素敵に継続中💋
落葉:12月11日頃〜
京都市では全体的に例年11月20日頃に紅葉のピークを迎えるも、本年は10日ほど遅れて12月に入ってようやく見頃を迎えた。
2023年度🍁
11月24日に「境内全体が見頃の最盛期を迎えています。」‥‥‥との記載があった。当寺の公式ホームページを見ると、
然るに11月24日から良くて一週間が見頃のピークと考え、11月末〜12月初め頃に散り紅葉が始まる‥‥という予測が成り立つ。
【平年】常寂光寺の紅葉の色づき始めや見頃のピークはいつ?
常寂光寺の紅葉は、例年以下のようなスケジュールで色づき、見頃を迎えます。
- 色づき始め:11月初旬(公式では11月2週目からと公知)
- 例年の見頃:11月中旬~11月下旬
常寂光寺の紅葉の種類
- ノムラカエデ
- イロハモミジ
- オオモミジ
- ヒロハモミジ
- イチョウ
‥‥などの種類の樹木が色づき、紅葉、黄葉を鮮やかに見せてくれます。
イチョウも植えられていますので、赤ばかりではなく黄色の葉が混じった他所と一線を画す雅やかな紅葉が観られる。
境内の紅葉する木々の本数
- カエデおよそ200本
小倉山全体がカエデの多い場所なので、山全体と合わせて最高級の紅葉が味わえるともっぱらの評判。
常寂光寺境内の紅葉見どころスポット一覧🍁
下掲写真は2021年12月08日に撮影したもの。
境内入口(山門)と紅葉
ピヨ🐣「常寂光寺」の寺号の由来
「常寂光(じょうじゃっこう)」とは、煩悩の概念を離れた寂滅と真智の光が満ちた世界のこと。この世界は「常寂光土」とも呼ばれ、娑婆に暮らす我々、人間の言葉では「極楽浄土」や「天国」と呼ぶ。つまり、仏が暮らす世界。
ともあれ、当寺の寺観そのものが、常寂光土にも例えられたことから、「常寂光寺」と号すに到ったらしい。
なお、百人一首の名歌人・藤原定家撰の歌から「軒端寺(のきばでら)」とも呼ばれるらしい。
忍ばれむ 物ともなしに 小倉山 軒端の松ぞ なれてひさしき
仁王門前の参道の紅葉の様子
先に言っておくと、当寺では所定の入山料金が必要💘
仁王門と紅葉
急遽、ふりかえって仁王門を撮影
背後に怒り狂った高坂桐乃の気配をピッコロ並みの察知能力で察知したのだが‥‥気のせいか。ふぅ 高坂とピッコロはどっから出てきた
関連記事:![]() 仁王門|常寂光寺
仁王門|常寂光寺
仁王門周辺の階段と紅葉の様子
常寂光寺の境内は山門(入口)から仁王門を経て山頂に到るまで傾斜地になっている印象がある。
もともと山の斜面だった場所をうまく活用し、斜面を掘削し、その合間々々に上掲写真のような休憩処や堂塔を配置している印象を受ける。
この土地の主人であった藤原定家、日禎(にっしん)、そして角倉了以らは風流・数寄者としても、さぞかし一流だったのであろぅ。ふぉっ、ふぉっ
本堂と紅葉
現在の常寂光寺本堂は、慶長年間(1596〜1615年)に小早川秀秋の支援によって伏見城の客殿を移築したものと伝わる。
🐣横額(扁額)
「御祈祷処」の揮毫は伏見常照院宮の筆らしい。
鐘楼と紅葉
庫裡と紅葉
定家山荘跡石碑と時雨亭跡と紅葉
藤原定家の小倉山荘「時雨亭」は当地には無かった?
‥‥‥という話もあるらしいが、どうやら常寂光寺境内北側の二尊院境内の南側に建っていたらしい。
これは現在、山頂の歌仙祠内にて奉祀される藤原定家像が、当地に移されてきた事実によって明らかにされた。
名もなき蔵と紅葉
再び名もなき休憩処と紅葉
春照坊と紅葉
滴る一条の懸樋と不動堂‥それに紅葉
🐣不動堂手前の名もなき弁天像?
二臂で左手に宝珠?、右手に宝棒?‥‥を持っている珍しい像容の弁天像。‥‥なぜこんなところに?
妙見堂と紅葉
やっぱり名もなき竹林と紅葉
この青々とした図太い逞しい竹!
‥‥‥今晩のオカズはタケノコの煮付けでKIMARI?
多宝塔と紅葉
関連記事:![]() 多宝塔【重要文化財】|常寂光寺
多宝塔【重要文化財】|常寂光寺
開山堂と紅葉
歌仙祠と紅葉
歌仙祠」と書いて「かせんし」と読む。”漢字”では”感じ”よく「謌僊祠」とも書かれる。(横額の文字に注目💋文豪・富岡鉄斎の筆らしい)
‥‥どうやらこの祠の中に”定価”ではとても売れねぇ!ほどの藤原”定家”像が、奉安されているとのこと。….ちょぃ無理あったか
展望台から観る紅葉と周辺市街
歌仙祠の上には市街を一望できる展望台が素敵にある。
ここまで苦労して登ってきて良かっとぅあ〜〜‥‥と心から思っちまぇるほどの善き景色が望める。
【オマケ】ライトアップ時の常寂光寺の様子
 上掲写真は嵐山花灯路にて開催されたライトアップ時の常寂光寺の様子を撮影したもの。
上掲写真は嵐山花灯路にて開催されたライトアップ時の常寂光寺の様子を撮影したもの。
嵐山花灯路の企画が廃止されてしまったので、今後、常寂光寺のライトアップを観られる機会は希少。
常寂光寺の拝観時間
- 9:00~17:00
(拝観受付終了時刻16:30)
また、大晦日(12月31日)には除夜鐘打公開も、パっぴょり素敵にある。
大晦日当日は22:30頃から除夜の鐘をつくための整理券が108枚配布され、23:45から除夜の鐘つきが始まる……など深夜から翌日にわたっての参拝が可能。
常寂光寺の拝観料金
- 大人(中学生以上)500円
- 小人 200円
- 障がい者の方 400円
常寂光寺の拝観料は、本堂の拝観料ではなく境内拝観料です。
拝観受付は、山門を潜った後、仁王門の手前にあるので、まずはここで受付をする。(御朱印希望も山門受付にて)
天龍寺から常寂光寺へのアクセス
🚉最寄駅
トロッコ嵐山駅(徒歩約05分)
JR嵯峨嵐山駅(徒歩約18分)
嵐電嵐山駅(徒歩約19分)
阪急嵐山駅(徒歩約28分)
🚌最寄りバス停
嵯峨小学校前 停留所(市営バスor京都バス)徒歩約10分
場所(地図)
🐣天龍寺から常寂光寺までの移動ルート
天龍寺から常寂光寺までは充分に歩いて行ける距離にある。
- 所在地:京都市右京区嵯峨小倉山小倉町3
ルートは下図のとおり。
天龍寺を正門から出て、竹林の小径を通って野宮神社側からアクセスすれば20分。
近道で行くならば、天龍寺を北門から出て、大河内山荘庭園前を通って歩くのがオススメ💘常寂光寺までは徒歩約10分。
とりわけ野宮神社へ立ち寄ったり、あらためて竹林の小径を観光したいのであれば、天龍寺を正門側から出るのが理想的💘
野宮神社も紅葉の名所の一つなので、あわせて観光してみてはいかがか。
天龍寺北門から大河内山荘にかけても、ある程度の竹林が見られますので、北門から早道をするのも良いでしょう。