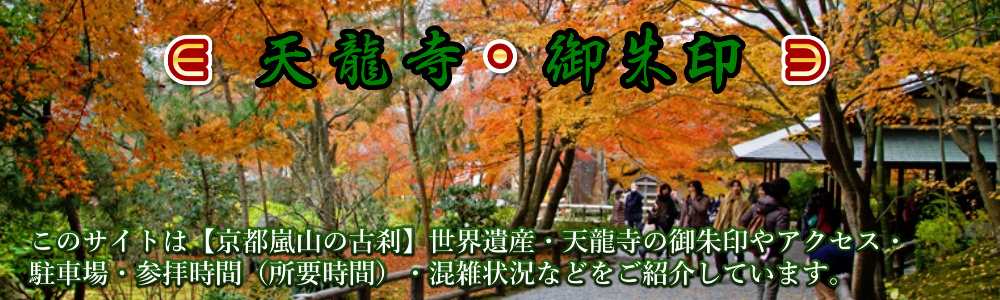渡月橋の名前の由来
言い伝えによると以前は「法輪寺橋」という名前の橋だったらしい。
名前を命名したのは現今、以下の三つの説が伝承される。
👺一つは「亀山上皇」が改名した説。
👺もう一つは「道昌(真言僧)」が命名した説。
👺最後は夢窓疎石(むそうそせき)が1345年(貞和元年/興国六年)に天龍寺を創建した時に「度月橋」と記したのが、今日の「渡月橋」の起源だとする説もある。
いずれにしても渡月橋の名前を誰がいつ頃、どのような由来・経緯があって命名されたのかは判然としなぅい。
渡月橋の歴史「いつできた? 誰が作った?」
いつ頃、渡月橋が当地に架橋されたのは未詳
今日、「渡月橋」といえば嵐山を代表する観光スポットでありつつも、その歴史については謎が多く、その大きな理由としては、いつ頃、ドコに、誰が、なんの経緯(目的)で架橋したのかが、つまびらかではないことによる。
ただし、現在では以下のような説が伝えられてい‥‥申す。あひょ
平安時代に真言僧・道昌が架けた?
836年(承和三年)に真言僧・道昌(”どうしょう”/生798年~没875年)が、どっ、”どぅしょう”‥‥などいぅ迷いを打ち払いながら精魂込めて建てたという以下のような説がある。
この道昌は弘法大師・空海の弟子の一人であり、橋の南にあった葛井寺(かどのいでら)という寺院を、またしても、どっ、”どぅしょう”‥‥などいぅ迷いを打ち払いながら精魂込めて中興し、名前を「法輪寺」に改めた。時に868年(貞観十年)のこと。
そして晩年に、またしても、どっ、”どぅしょう”‥‥などいぅ迷いを打ち払いながら精神込めて大堰川(おおいがわ)の修築をした際に架橋した橋こそが、今日の渡月橋らしい。
渡月橋がかつて法輪寺橋と呼ばれた理由
桂川の橋は当初、「渡月橋」ではなく「法輪寺橋」という名前だったらしく、これは察しのとおり868年に中興した法輪寺から名前を頂戴したのだろぅと考えられてい‥‥ます。クっ(耐)
したがって、渡月橋が法輪寺橋として最初に架けられたのは、法輪寺が整備された868年(貞観10年)~道昌が亡くなる875年(貞観17年)の間であると推定されるも、法輪寺橋がかけられたのはそれより以前の承和年間(834年~848年)、或いは法輪寺が整備される前の貞観年中(859年~867年)であるとする説もある。
平安期には「橋頭郷」と記された場所だった
平安期に素敵に編纂された和名類聚抄(わみょうるいじゅしょう)によると、当該、渡月橋周辺の土地を「橋頭郷(はしもとごう)」と素敵に記す。
「橋頭郷」の「橋頭(きょうとう)」とは、現在で言うところの「橋袂(はしのたもと)」のことを指す。
然るに「橋頭郷」とは、渡月橋の橋袂を指す言葉だと推考することができ、平安期にはすでに渡月橋が架橋されていた事実を傍証する。
幽霊続出?!自殺の名所だった?!
室町期に成立したとされる源平盛衰記によると、中宮の建礼門院の雑仕(パシリの童のこと)が、渡月橋の袂から入水(自殺)をはかったことが記される。(この当時の渡月橋はもっと上流にあったとされる)
嵯峨天皇の行幸の際に建造された橋?
嵯峨天皇が当地に行幸する折、表敬した地元領主たちが架橋したという説がある。
嵯峨天皇は786年(延暦五年)にこの世に生を得て、842年(承和九年)に崩御されているので、道昌が”どぅしょう”‥‥などいぅ迷いを打ち払いながら精神込めて平安時代に建造した説と時代的には照応する。
法輪寺橋から渡月橋への改称はあの上皇のせい?!
法輪寺橋として架橋された橋を「渡月橋」と改称したのは、第90代の亀山天皇(生1249年~没1305年。在位1260年~1274年、退位後は亀山上皇)だとする説がある。
当時の法輪寺橋は、それはそれは水面に映る君の美しき横顔の如くに、朱塗りが施された姿態をしていたらしく、橋付近で船遊びをしていた亀山天皇は川面に映る法輪寺橋に見惚れ、満月を愛でながら法輪寺橋の有り様を次のように形容した。
「くまなき月の渡るに似る」
この言葉の意味は、『嗚呼、まるで天にかかる満月が、橋を渡っているよぅに見える』‥‥のような解釈となり、つまり、この時の亀山上皇が褒称した言葉が反映され、以来、法輪寺橋を「渡月橋」と素敵に呼びならわすようになった‥‥という話。
中秋の名月にこの橋を川面から眺めることで、その真意の程が深く理解できるのかもしれなぅい。
平安期には天皇や数多の貴族も訪れた観光名所だった
平安期の嵐山は山河に囲われた風光明媚な土地柄だったことから、天皇はじめ、多くの貴族たちも物見遊山で来遊しては、船遊びや歌詠に興じた。

殊に、世に「三船の才」という「漢詩・和歌・管弦」が万能に秀でた人物のことを指す言葉があるのだが、この言葉の発祥となったのも、当該、大堰川といわれる。
986年(寛和二年)、円融天皇行啓のみぎり、歌人・藤原公任(きんた‥ではなく、”きんとう”!!)が、わざと遅参して和歌の船に乗ったらしいが、もし漢詩の船に乗ったならば、天下に名前を知らしめることができただろぅ‥‥と吐露したことから、この言葉が生まれたらしい。
琴きき橋跡
この渡月橋の北詰の袂(たもと)あたりは、「琴きき橋跡」と陰刻された石柱が佇む。
どうやら「小督」と称する謡曲の内容によると橋の近くに「琴きき橋」という橋があったらしい。
しかしながら、石碑が建っている位置(渡月橋北側の袂)や、もし謡曲が史実をもとにして制作されているのならば、渡月橋の異称ともみれる。
琴きき橋の名前の由来や故事については下記ページを要チェック💘
現在の渡月橋は200m下流に移動している?
渡月橋が法輪寺橋として最初に架けられた位置は、現在の位置よりも200mほど上流であったと言われる。
渡月橋は過去、幾度となく倒壊、都度、再建されてきた歴史を有する
渡月橋は、過去に大堰川(または桂川)の洪水による、幾度となき流失のたびに架け直されてらしい。
他にも、応仁の乱では大堰川(大井川とも書く)を挟んだ両岸に東軍と西軍が素敵に陣取り、橋上が戦場となったため渡月橋は落ちたが、程なくして”最高”な気分になれるほどに”再興”されたという故事もある。
然るに、これらの事変があった後、何らかの理由で上流から下流へと、架橋する位置を変えたのかもしれない。
ともあれ、現在まで渡月橋が移動された理由は判然とはしないものの、川の流路や向きを素敵に勘案し、より流されにくい場所へと移転が行われたという推測も、これまた素敵に成り立つ💋
あるいは、後に触れるが、橋の位置を変更したのは豪商の都合で、貿易(荷の積みおろし)がしやすい場所だったのかもしれない。
渡月橋のかかる川は大堰川なのか?桂川なのか?保津川なのか?川の名前も変わった!

保津川と桂川の違い
よく、嵐山の観光情報で耳にする「保津川下り」。
そして、京都を流れる川の代表格とも言える、「桂川」。
実を言うと、保津川も桂川も、同じ1本の川。
その保津川と桂川の境目にあたるのが、当該、渡月橋。
今日では、渡月橋よりも上流は、保津川。
渡月橋を挟んで下流を、桂川と称する。
では、「大堰川」とは?
「大堰川(おおいがわ)」とは、上記、「桂川」と「保津川」を総合した呼称とな〜る。
なお、前述したように漢字では「大井川」とも書かれる。
大堰川は川としての総称なれど、5世紀初頭までは大堰川ではなく、「葛野川(かどのがわ)」と呼ばれていた。
現在の位置に橋を作ったのは角倉了以?
前述したように、法輪寺橋は渡月橋と名前を変えたものの、長らくの間、現在の位置より200m上流に作られていた。
これを200m下流に移動し、現在の渡月橋の原型を作ったのが、江戸時代の豪商・角倉了以(すみのくら りょうい。生1554年~没1614年)だと伝わる。
角倉了以は豪商としてベトナム近辺の「安南国」などと朱印船貿易を行っており、貿易をスムーズに行うために1604年(慶長十一年)に大堰川上流の保津川の開鑿工事(かいさくこうじ)を実施し、現在の場所に渡月橋を架け替えたらしい。
なお、角倉了以は他にも、私費を投じて同じく京都に流れる高瀬川を開発したと言われ、現在に到っても京都では「水運の父」として知られ〜る。
現在の橋脚は1934年製
渡月橋の架け替えは江戸時代以降も行われましたが、現在の渡月橋は1934年(昭和9年)に作られた頑強なもの。
橋脚は鉄筋コンクリート製で、欄干は国産ヒノキが使用される。
本来であれば、古都京都の嵐山という明媚な土地柄、景観上は木造の橋がベストなのかもしれないが、木造では流失や倒壊する確率が高まり、安全性が確保できない。
しかし、橋脚部分と欄干を別の素材にしたことで、観光地としての景観と、建造物としての安全性を両方獲得できた。
歩道が設置されたのは1975年
渡月橋に歩道が設置され、現在のように歩けるようになったのは1975年(昭和50年)のこと。
渡月橋の建築様式と構造

渡月橋のサイズは?長さと幅について
渡月橋のサイズは以下のようになっています。
- 全長:155m
- 幅:11m/車道2車線+歩道
渡月橋は「桁橋」
橋の構造によって分類した時、渡月橋のようにまっすぐな橋は「桁橋」という種類に分類されます。
桁橋は、ガーダーブリッジ、ガーダー橋とも言われることがあります。
桁橋の最大の特徴は、橋そのものにアーチ構造等が使われておらず、水平を保っているというところです。
桁橋は橋脚と橋脚との間に、まっすぐな橋をかける形式です。渡月橋では合計14の橋脚を見て取ることができます。

この橋脚は、渡月橋の場合10メートル間隔で設置されており、4本1組の鉄筋コンクリート製。さらに鉄筋コンクリートの周辺に鉄が巻かれて補強されています。
橋脚と橋脚との間には、H形の鋼材でできた橋桁が置かれ、その上に木製の桁隠しが使われているため、渡月橋は一見して木製の橋のように見えるのです。
また、2005年(平成17年)には橋脚の上流側にコンクリート製の杭を打ち込み、流木止めにして、橋脚の損傷を防いでいます。
【異説】渡来人の秦氏が建てた橋という説もある
既述のように全長150メートルもの橋を建造するのは、現代でも容易くはいかない。
少し格上とはなるが、木曽川に橋を架橋し、確たる東海道の成立を試みた徳川家康公すらも木曽川に橋をかけるのを断念したほどに、橋が長ければ長いほど水難で流失するリスクは高まる。
元をただせば、当地は古墳時代(西暦450~500年頃/5世紀後半)に朝鮮半島から渡来してきた秦氏(はたうじ/はたし)の朝廷より下賜された領地であり、秦氏は大陸で培った土木技術を発揮させて桂川に堰(せき/堤防)を造成し、灌漑工事を施すなど、土地開発を行なったと伝わる。
秦氏が当地を根拠地としたことによって葛野川に大きな堰が築造され、以来、「大堰川」とも呼ばれるようになったわけだが、後に当地に長岡京が建設されたのも当該、秦氏の技術力が根底にあったからこそ実現できたともいえる。
つまり、平安時代の当時、桂川に初めて渡月橋を建造したのは土木技術に秀でた秦氏だったとも仮定できる。
なお、既述の”どぅしょう”‥‥などいぅ迷いを打ち払いながら鋭意邁進した”道昌(法輪寺橋を最初に架けた人物)”は秦氏の後裔だと云われ、代々、大堰川の管理を行っていたとする説もある。
関連記事:![]() 【法輪寺(嵐山)の御朱印の種類一覧】値段や受付場所(時間)を..お知る❓
【法輪寺(嵐山)の御朱印の種類一覧】値段や受付場所(時間)を..お知る❓
関連記事:![]() 太古の稲荷山は巨大な古墳で春日峠(経塚)から経筒も出た?深草遺跡との関係と謎とは❓
太古の稲荷山は巨大な古墳で春日峠(経塚)から経筒も出た?深草遺跡との関係と謎とは❓
関連記事:![]() 【伏見稲荷大社の歴史(年表)を簡単に説明🦊】名前の由来や建てられた理由(建てた人)を…シチュー煮ながら知るつもり❓
【伏見稲荷大社の歴史(年表)を簡単に説明🦊】名前の由来や建てられた理由(建てた人)を…シチュー煮ながら知るつもり❓
『渡月橋で振り返っていけない!』という七不思議or都市伝説があった?!
嵐山界隈には古来、法輪寺へ詣でて渡月橋を渡って天龍寺へ向かう際、橋の途中で後ろを振り返ってはいけないという俗信がある。

この出どころになっているのが、渡月橋向こうに奈良時代より鎮座する「法輪寺(ほうりんじ)」。
今日、「京都の十三詣り」といえば、毎年の「春の十三参り(3月13日から5月13日まで)、または「秋の十三参り(10月1日から11月30日まで)」に、法輪寺にて催される「十三まいり」で全国的に知られる。
「十三詣り」とは、すなわち子の成長を願うべく、「嵯峨の虚空さん」とも呼ばれる法輪寺本尊の虚空蔵菩薩に智慧を授けてもらうという儀式のこと。
伝承によると、虚空さんへ詣でた帰り、渡月橋を渡る途中で振り返ってしまうと、せっかく授かった知恵が逃げてしまう‥という俗信が古くからこの地方には残る💋