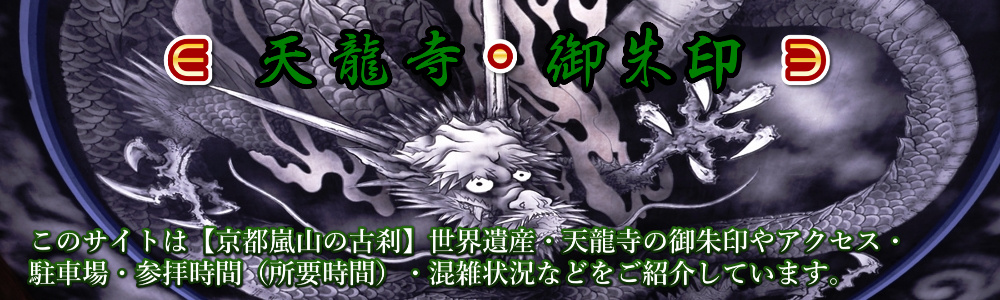世界遺産・天龍寺へ、京都駅からアクセスする方法をご紹介します。
天龍寺の最寄り駅は、京福電鉄嵐山線(嵐電)の「嵐山」駅です。ただし、京都からはJR山陰本線「嵯峨嵐山」駅を利用するのが良いでしょう。
アクセスしやすい場所に、バス停もありますので、バスでのアクセスもおすすめですよ。駅からの徒歩ルート、駐車場に関しても詳しくご案内します。
京都駅から天龍寺の方角・距離など
京都駅から見て、天龍寺は北西の方角にあります。
車で訪れた場合は、走行距離はおよそ10kmです。渋滞がなければ30分ほどのルートです。
一方、電車では京都駅から標準16分の乗車。電車を降りてから13分ほど歩きます。
では、電車での行き方から確認してみましょう。バス、車でアクセスしたい方は記事をすこし下までスクロールしてくださいね。
京都駅から天龍寺までの電車でのアクセス
京都駅から天龍寺まで電車で行くには、JR山陰本線を利用します。
京都駅から天龍寺まで電車で!(JR嵯峨野線利用)
京都駅(31・32・33番線)
↓ JR山陰本線嵯峨野線
↓ 乗車16分 240円
嵯峨嵐山駅
↓ 徒歩13分
天龍寺
天龍寺の公式サイトには、最寄り駅筆頭に京福電鉄嵐山線(嵐電)の「嵐山駅」が挙げられていますが、嵐電は京都駅を通りませんので、京都駅からアクセスしたい時は、JR山陰本線(嵯峨野線)の「嵯峨嵐山駅」が便利です。
嵯峨嵐山駅から天龍寺への徒歩ルート
嵯峨嵐山駅から天龍寺までは、距離にして900m、時間にして11~13分ほどです。
嵯峨嵐山駅を出て、南側へ直進し、「天龍堂」の建物の先を右折します。
あとは、まっすぐ直進するだけで「大本山天龍寺」の門前に到着することができます。
嵐電の嵐山駅から天龍寺へアクセスしたい場合は?
観光チケットや、観光ルート、徒歩距離等の事情で、嵐電の嵐山駅から天龍寺へアクセスしたいこともあります。
JR山陰本線嵯峨野線
嵯峨嵐山駅
↓ 徒歩13分
天龍寺
京福電鉄嵐山線嵐電
嵐山駅
↓ 徒歩5分
天龍寺
このように、電車を降りてから天龍寺までの徒歩距離は、嵐電の嵐山駅のほうがはるかに短いのですが、嵐電は京都駅を通っていませんので、京都駅からのアクセスには向きません。
嵐電に乗車したい場合は、
- 京都市営地下鉄東西線「太秦天神川駅」から乗り換えで「嵐電天神川駅」から嵐電に乗車
することで、嵐電の嵐山駅にアクセスできます。詳しい行き方は以下のようになります。
京都駅から天龍寺まで電車で!(京福電鉄嵐山線=嵐電・嵐山駅利用)
京都駅
↓ 京都市営地下鉄烏山線
↓ 乗車8分
烏丸御池駅(からすまるおいけ)
↓ 京都市営地下鉄東西線
↓ 乗車8分
↓ 京都市営地下鉄ここまで260円
地下鉄・太秦天神川駅下車
↓ 徒歩1分
↓
嵐電・嵐電天神川駅乗車
↓ 嵐電
↓ 乗車14分 220円
嵐山駅
↓ 徒歩5分
天龍寺
※電車の乗車料金の合計は480円
嵐電の嵐山駅から天龍寺へは、徒歩でおよそ5分です。地図は以下のようになります。
マップでは6分と出ていますが、実際には天龍寺入口の門は、上の赤い★マークの位置にあります。
したがって、嵐電嵐山駅から天龍寺の入口までは、実際には徒歩1~2分です。ルートも門まではほぼ直進で、迷う気遣いはありません。
京都駅からアクセスするには、多少面倒な部分がありますが、どこか観光の途中で嵐電に乗車できるのであればおすすめできるルートです。
京都駅から天龍寺までのバスでのアクセス
天龍寺までバスでアクセスしたい時は、天龍寺に近い
- 嵐山天龍寺前
- 京福嵐山駅前(=嵐電嵐山駅前)
以上、2つのバス停を利用することができます。
これら2つのバス停は2つとも隣り合って立っていますので、実質的には同じ場所です。また京都バスのバス停は、正式には「京福嵐山駅前」なのですが、実際には「嵐山天龍寺前」と書かれています。市バスのバス停にも「嵐電嵐山駅」とありますね。
各バス停に停車するバスは、以下のようになっています。
市バス「嵐山天龍寺前」
11、28、93番
※京都駅から乗れるのは【28】
京都バス「京福嵐山駅前」
61、72、73、83、86番
京都駅から市バス【28】を使う天龍寺へのアクセス
↓ 京都市営バス28系統(京都駅前の時刻表はこちら)
↓ 始発 平日、土曜休日ともに6:31
↓ 乗車44分 230円
嵐山天龍寺前
↓ 徒歩5分
天龍寺
京都駅前は乗り場の数が多く迷いがちですが、塩麹通側のC6乗り場へ回りましょう。
近くには伊藤久右衛門京都駅前店、ホテル法華クラブ京都などがあります。
28系統は現在、6:30の始発から、昼間はおおむね1時間に3本、20分間隔(朝夜除く)で運行されています。運行時刻は変更になる可能性がありますので、ご自身でご確認ください。
京都駅から京都バス【72、73】を使う天龍寺へのアクセス
↓ 京都バス72系統または73系統(京都駅前の時刻表はこちら)
↓ 始発 平日6:55 土曜7:10 休日7:30
↓ 乗車53分 230円
嵐山天龍寺前
↓ 徒歩5分
天龍寺
こちらのルートも、京都駅からの乗り場は京都市営バスと同じC6です。
運行間隔は時間により違いますが、昼間は1時間に1~2本の運行となっています。
バスの乗り場も降車場も同じですから、早くきたバスに乗るというスタンスで問題ないでしょう。
バスを降りてから天龍寺までの徒歩アクセス
嵐山天龍寺前のバス停は、嵐電の嵐山駅の目の前にあります。
バスを降りてまっすぐ、嵐山駅を右ななめ後ろに歩けば天龍寺の入口の御門に到達します。門は上の地図の★マークのところですから、実質的には徒歩1~2分です。チョロイネ♥
京都駅から天龍寺までの車でのアクセス
京都駅から天龍寺までは、車で30分強の距離です。走行距離にするとおよそ10kmになります。
具体的なルートは以下のとおりです。
京都駅から天龍寺までの自動車ルート
京都駅を、国道24号線で北上
↓ 道なりに直進3分
烏丸五条交差点を左折
↓ 国道9号線を直進10分
葛野西通五条交差点を右折
↓ 直進1分
「古美術ギャラリー石田」の看板のある信号を左折、府道113号線に入る
↓ 道なりに直進2分
上野橋交差点で左折、すぐ右折
↓ 道なりに直進5分
四条通にぶつかったらT字路を左折
↓
すぐ罧原(ふしはら)堤四条交差点を右折
↓ 道なりに府道29号線を直進 10分
渡月橋信号を右折
↓ 直進2分
左手に天龍寺駐車場あり
※各所要時間は概算です。混雑状況、車のスピード等により異なります
天龍寺の駐車場の収容台数は100台です。
駐車料金は、乗用車が1,000円/1回です。
また営業時間は8:30~17:30(10/21~3/20までは8:30~17:00)となっています。
繁忙期は満車になりますので車でのアクセスはおすすめできません。
また、紅葉のシーズンは天龍寺前で交通規制が行われ、片側交通での混雑が予想されます。
京都駅から天龍寺までタクシーでどれくらい?
京都駅から天龍寺までのタクシー料金はおよそ3,340円です。
4人で乗車した場合は、1人835円になりますので、片道230円の最安バスルートと比較するとだいぶ高い印象です。
ただその分、自分で徒歩移動しなくて良いメリットもありますので、もし必要な方はタクシーを手配しましょう。
京都の主なタクシーは以下のとおりです。
- MKタクシー京都駅八条口のりば
TEL:07-5662-1139 - ヤサカタクシーコールセンター
TEL:07-5842-1212 - 日交タクシー
TEL:07-5681-5551
なお、上の車アクセスでご紹介した天龍寺駐車場ですが、タクシーなら500円/2時間で駐車させてくれますので、帰りのタクシーをつかまえる自信のない方は、駐車場に停めておいていただくという方法もあります。(待機料は別途御確認くださいね)。
京都駅から天龍寺まで最安値はバス!早いのは電車
京都駅から天龍寺までのアクセスルートをご紹介してまいりました。
最も安いのは、バスの230円。最も早いのは、JR山陰本線嵯峨野線を用いたおよそ30分のルートです。
車でのアクセスは、順調であれば30分強で到着しますが、なにしろ観光地ですので混雑は避けられない一面も。もしお車でアクセスされる場合は、ある程度の混雑は予想の上で、お時間に余裕を持ってお越し下さいね。
スポンサードリンク -Sponsored Link-
当サイトの内容には一部、専門性のある掲載があり、これらは信頼できる情報源を複数参照し確かな情報を掲載しているつもりです。 また、閲覧者様に予告なく内容を変更することがありますのでご了承下さい。